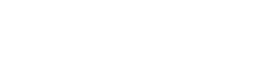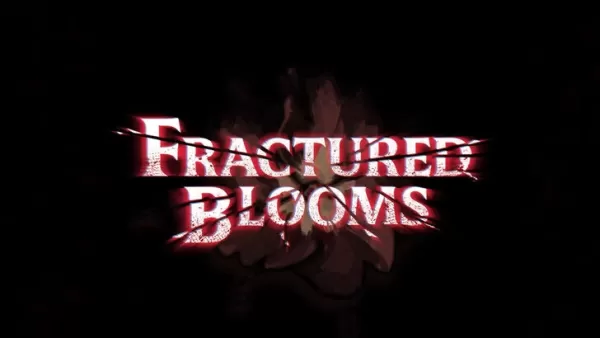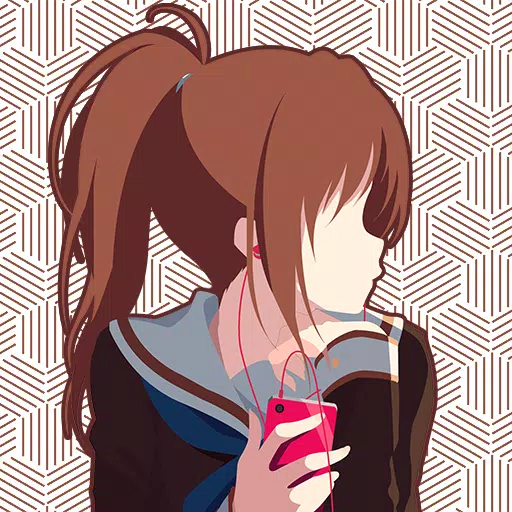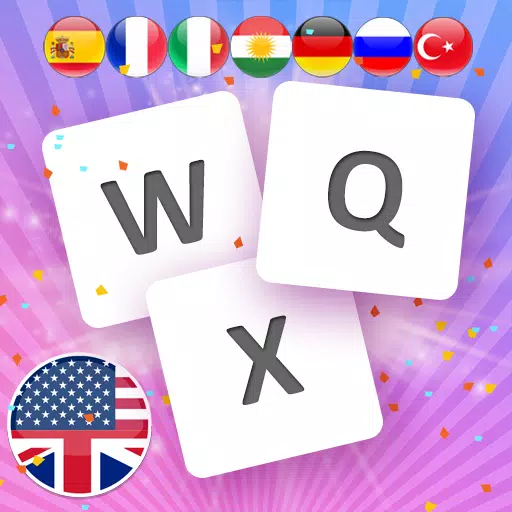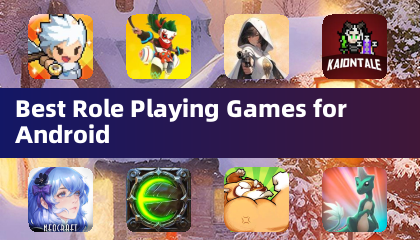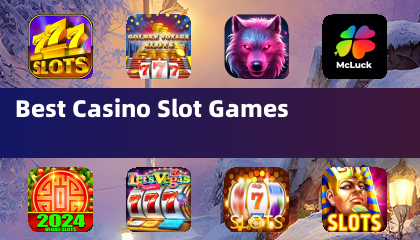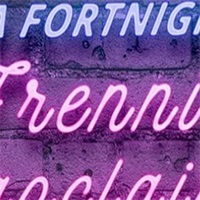予期せぬHaloとの共通点
『Doom: The Dark Ages』プレビューセッションの中盤、私は思いがけず『Halo 3』との類似点を感じた。特に衝撃的だったのが、サイボーグドラゴンに騎乗し、悪魔の軍艦に機関銃を浴びせるシークエンスだ。防御システムを無力化すると、翼を持つ獣を着陸させ、チェーンソーで肉を切り裂くように船内を蹂躙。乗員を血の海に変えてから、船体を撃ち抜いて脱出した。
マスターチーフの象徴的なスカラブ戦闘との共通点は明らかだった。コヴナント巡洋艦がオカルト軍艦に、ホーネットがホログラフィックドラゴンに置き換わっているが、「空中爆撃から肉薄のボーディングアクションへ」という興奮の流れは同一だ。驚くべきことに、2時間半のデモプレイ中、これが唯一のHalo的な瞬間ではなかった。『The Dark Ages』はDoomの残忍な戦闘DNAを保ちつつ、2000年代後半のシューター作品の特徴——劇的なカットシーン、ビークルシークエンス、爆発的なセットピース——を積極的に取り入れていた。
伝統からの離脱
デモでは4種類の異なるゲームプレイを体験した。序盤のミッションだけが、近年のDoom作品らしい緻密なアリーナ設計と圧倒的なペースを維持していた。その後は巨大メカの操縦、サイバードラゴンの指揮、秘密と強敵が潜む広大な戦場の探索が続く。
これは「純粋な戦闘の卓越性」に焦点を当てたシリーズの方向性から劇的な転換を意味する。むしろ『Halo』や『Call of Duty』の古典を思わせるミッションの多様性——もちろんDoom独自の過激なフィルターを通して——を取り入れた作風だ。皮肉なことに、この方向性は2013年にキャンセルされた『Doom 4』プロジェクト(当初はより映画的で軍事風の作品として構想されていた)を彷彿とさせる。
映画的アプローチの登場
デモは異例に長いカットシーンから始まる。ラヴィッシュなビジュアルとドラマチックなストーリーテリングでアルジェント・ダヌールの設定を説明する——前作の環境ストーリーテリングとは対照的だ。『Halo』のマリーンのようにNPCのナイトセンティネルが戦場に登場するが、幸いにもゲームプレイの核心が損なわれることはない。カットシーンはあくまでミッションの前後に配置され、Doomの代名詞である猛烈なペースを乱さない。
多様性という諸刃の剣
アトランメカやドラゴンシークエンスは紛れもない見せ場だが、Doomの精巧なガンプレイに比べると機構的に浅い。悪魔の怪獣との格闘はスケール感に優れるが、通常戦闘のような戦略的深みに欠ける。空中戦も視覚的華やかさの割に制約が目立った。
「包囲戦」ミッションはこれらの弱点を挽回する。広大な戦場でDoomの戦術的ガンプレイを拡張することで、各武器の有効射程の再考を迫り、砲撃へのシールドタイミングを重要にし、機動性の選択に新たな戦略的側面を与えた。
大胆な実験
『The Dark Ages』は興味深い矛盾を提示している——10年前ならDoomのアイデンティティにそぐわないと判断されたコンセプトを復活させつつ、シリーズ史上最高の戦闘システムと融合させているのだ。実験的な要素の一部は機構的に物足りないが、中核のゲームプレイは極めて洗練され、興奮を誘う。
これらの異質な要素が結束して一貫した体験を生むかは未知数だ。しかしid SoftwareがDoomの境界線を大胆に再解釈しつつ、その暴力的本質を守ろうとする姿勢は、5月15日の発売をゲーム史上有数の創造的挑戦に仕立て上げる可能性を秘めている。